相続

相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、当該遺産分割協議が成立した日から3年以内)に相続の登記申請をすることが義務になりました。正当な理由がないにもかかわらず相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
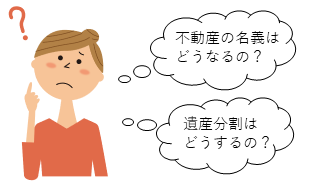
※2024年4月1日より前に不動産を相続して相続登記をしていない場合も義務化の対象ですが、この場合は2027年3月31日までに相続登記をすればよいことになっています。
尚、諸事情により期限内に遺産分割や相続登記の申請ができない場合は、「相続人申告登記」をすることで相続登記の義務を果たすことができます。相続人申告登記とは、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるように新設された制度で、申し出をした相続人の氏名や住所が登記されます。
相続登記までの一般的な流れ
身近な人が亡くなり相続人となった場合は、様々なお手続きをする必要があります。
葬祭手続き、保険や年金等の手続き、戸籍の収集、相続財産の調査、不動産や預貯金の名義変更や解約、相続税の申告等です。
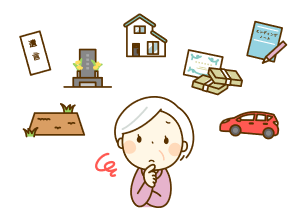
亡くなられたご家族の構成などにより手続きや必要書類は異なりますが、ここでは、亡くなった方が不動産を所有していた場合の相続開始から相続登記までの一般的な流れについて、遺言書がある場合と遺言書がない場合に分けてご説明いたします。
遺言には数通りの方式がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。
| 自筆証書遺言 | 遺言全文、作成日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです。 作成した遺言書を、自己で保管する以外に、「自筆証書遺言書保管制度」を利用して法務局で保管してもらう方法があります。 |
|---|---|
| 公正証書遺言 | 証人2人以上が立ち会って、公証人に遺言内容を口述し、その内容を公証人が作成する遺言書のことです。 |
「自筆証書遺言書保管制度」を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。
※「自筆証書遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言は、検認手続きは不要です。
遺言書の内容を実現するためには、その内容を執行する遺言執行者が必要となる場合があります。遺言者は、遺言書の中で遺言執行者を直接指定したり、第三者に遺言執行者の指定を委任することができます。
遺言執行者についての記載がない場合は、相続人が遺言の内容を執行するか、相続人又は受遺者等の利害関係人が、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることができます。
遺言書の内容に基づいて、遺言執行者が登記の手続きを行います。
亡くなった方の相続人を確定するため、亡くなった方の生まれてから死亡するまでの全ての戸籍謄本と住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。
相続財産とは、亡くなった方が死亡時に所有していたプラスの財産とマイナスの財産のことで、遺産ともいいます。プラスの財産には、現金、預貯金、土地、建物、車、株式などがあり、マイナスの財産には、借金、未払い金などがあります。
相続をする方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。原則として、相続の開始又は自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、限定承認又は相続放棄の手続きをしなければ、単純承認をしたとみなされます。
| 単純承認 | 預金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナス財産も含めて、すべて相続する方法 |
|---|---|
| 限定承認 | 借金などのマイナスの財産を差し引いても、預金などのプラスの財産が残る場合のみ相続する方法 |
| 相続放棄 | プラスの財産とマイナスの財産の、すべての財産を相続しない方法 |
相続人が複数いる場合、相続財産について誰がどれを相続するのかを、相続人全員の協議で決めることができます。その協議のことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申立てをして、遺産分割の調停又は審判の手続きをすることができます。
相続人が登記の手続きをします。
